手元供養とは、故人の遺骨や遺灰を分骨し、自宅など身近な場所で供養することを指します。従来の墓地や納骨堂に納めるのではなく、小さな骨壺やペンダント、オブジェなどに遺骨の一部を納め、日常の中で供養するスタイルが特徴です。様々な宗教観から従来の形式にとらわれない形を選択する人が増えているようです。そんな手元供養の魅力を紹介していきます。
お墓に埋葬しなくてもいいの?
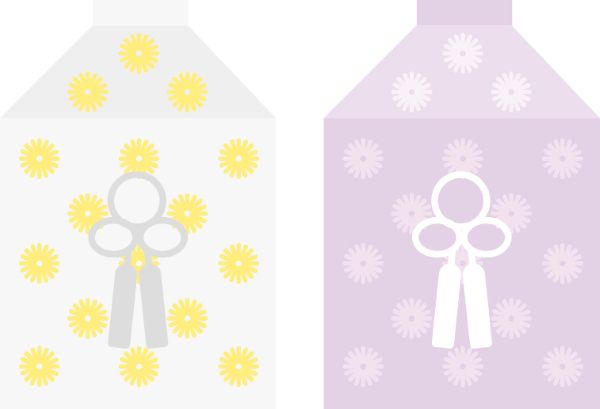
通常はお墓や納骨堂に埋葬される遺骨なので、分骨と聞くと「故人が迷子にならないかしら」とか「成仏できないのではないか」という不安に思う人もいるでしょう。しかし法律的に違法とはされていません。またお釈迦様が入滅されたとき、その遺骨である仏舎利が8つの国に分配されたという経緯からも仏教において分骨は古くから行われてきたことであり、良くないこととはされていないようです。そんな分骨の保管方法は二種類あります。
1.遺骨や遺灰の全てを自宅で保管する(=全骨)
2.正式なお墓を持っており、墓地や寺院へ納骨した上で一部だけ自宅で保管する(=分骨)
手元供養のメリット、デメリット

メリット
故人をいつもそばに感じられる
遺骨の一部を小さな骨壺やアクセサリーに納め、持ち歩くことで家族がいつでもそばに感じられるようになります。
自由な形で供養できる
特定の宗派や形式に縛られず、自宅で供養ができるため、自分なりの方法で故人を偲ぶことができます。
お墓をもたなくてもよい
墓地の維持管理が難しい、遠方の墓に行くのが困難、などのお墓を持つ負担だけでなくお墓を購入・維持する費用(永代使用料、管理費)などの経済的な負担も減らすことができます。
デメリット
周囲の理解が得られにくい場合がある
手元供養はまだ一般的ではないため、家族や親戚から理解されにくいことがあります。そもそも手元供養を推奨していない宗派もありますし、その考えのもと 遺骨を分けることを好まない宗教的な考えを持つ人もいます。
紛失、盗難のリスク
手軽に持ち歩けることが魅力ですがその分、管理や保管に注意しなければなりません。出先での紛失や盗難、劣化などのリスクもあります。
手元供養の方法
ミニ仏壇、ステージ仏壇

手元供養用に作られたコンパクトな仏壇を設け、遺骨や位牌、写真などを置いて供養します。家具の上など、置き場所を選ばず省スペースで祈りの場を作ることができます。扉のない仏壇、はたまたステージタイプのものなど今までの仏壇の概念を覆すようなスタイリッシュな仏壇が多く販売されています。
ミニ骨壺

骨壺は火葬した後の遺骨を納めるための容器です。分骨・手元供養用の骨壺は2〜4寸で一般的な納骨用の骨壺(5~7寸)と比べるとかなり小さく、片手に収まるサイズから、両手で包み込めるサイズくらいのものが好まれているようです。
アクセサリー
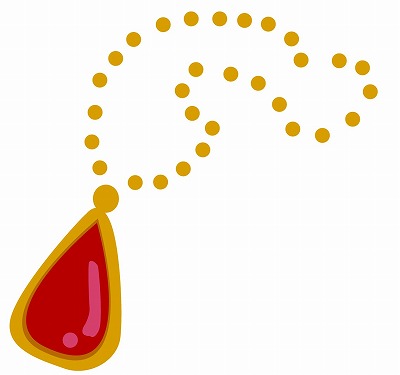
遺灰や遺骨の一部をペンダントや指輪に納め、身につける方法です。アクセサリーというと、女性は身に着けやすいですが男性には抵抗があるかもしれません。そんな方向けにキーホルダーやカプセルといったものもあります。
分骨に必要な手続き

分骨には必要な手続きがあり、その内容や必要書類である分骨証明書の発行元は分骨するタイミングによって異なります。おおまかに分けると火葬の際(納骨前)に分骨を行うか、火葬後(納骨後)に分骨を行うかの二つに分かれます。
火葬のタイミングで分骨を行う場合
火葬の際に分骨する場合は、火葬場で分骨証明書を発行してもらいます。あらかじめ分骨することが決まっているのなら事前に葬儀社や火葬場の担当者に分骨したい旨を伝えておくと後々の手続きがスムーズです。この時、既に骨壺が必要になるので準備しておきましょう。証明書の発行手数料は1枚数百円ほどです。
火葬後に分骨を行うとき
一度お墓に納めた遺骨を後から分骨する場合は、遺骨を納めている霊園や寺院で分骨証明書を発行してもらいます。墓地がある霊園の管理者や寺院の住職に分骨をしたい旨を伝えて遺骨を取り出します。遺骨を取り出すためにお墓を動かさなければならないので石材店に作業を依頼する必要があります。目安として2万~3万円程度の費用がかかります。遺骨の取り出しには管理者の立ち合いが必要だったりすることからも、一度埋葬した遺骨を取り出すのは費用も手間もかかることがわかります。
まとめ

供養の形は多様化しています。遺骨はお墓に埋葬し、お彼岸やお盆にはお墓参りをして故人を偲ぶというが一般的な風習としてありましたがお墓の管理や継承が難しい現代では新しい供養の形として手元供養を選択肢に入れる家庭が増えています。家族や親族のなかには、通常通りの供養を望んだり、手元供養に反対したりする方がいるかもしれません。まずは手元供養する前に家族や親族へ希望を伝え、全員が納得したうえで決定するのが大切です。しきたりにとらわれず故人を身近に感じられるのが最大のメリットである手元供養を新しい供養方法の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。


