春と秋、年に二度訪れる「お彼岸」は、仏教においてご先祖様を供養する大切な時期です。日本独自の風習であるお彼岸には、家族が集まり、仏壇を整え、墓参りをして、先祖への感謝と祈りを捧げます。この記事では、お彼岸の仏壇飾りについて、花の選び方や仏具の配置、また注意すべき点を詳しく解説します。
お彼岸とは
お彼岸は、春分の日と秋分の日を中心とした7日間で行われます。初日を「彼岸入り」、中日を「彼岸の中日(春分・秋分の日)」、最後を「彼岸明け」と呼びます。太陽が真東から昇り真西に沈む中日は、あの世とこの世がもっとも近づくとされ、特にご先祖様への供養が重要とされる日です。
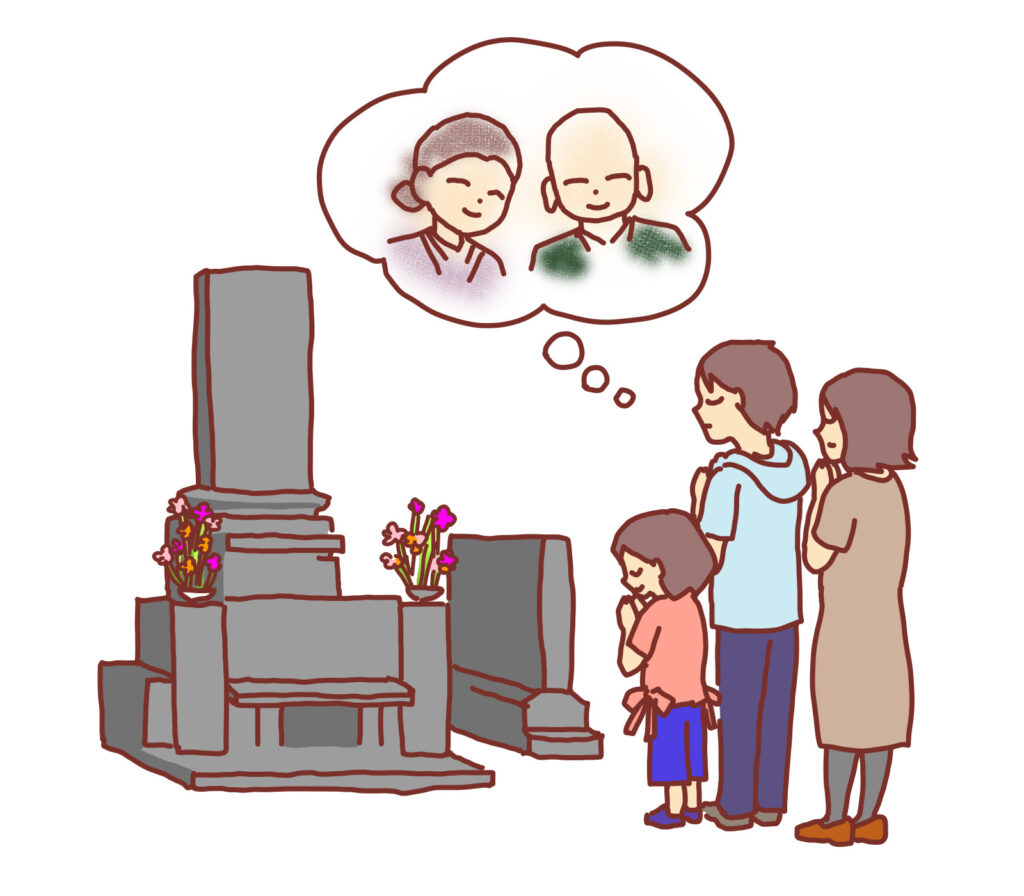
仏壇飾りの基本構成
仏壇は、ご本尊(阿弥陀如来やご本山の宗祖像など)とご先祖様の位牌をお祀りする神聖な場所です。通常の飾り方は宗派によって多少異なるものの、お彼岸に向けては一層丁寧に整えることが求められます。以下は一般的な配置と飾り方です。
ご本尊と位牌の配置
ご本尊(仏像や掛け軸)は、仏壇の中央、最上段に安置します。

位牌は、ご本尊よりも一段下の段に並べて配置します。ご先祖様が複数いる場合、古い順に奥から並べるのが一般的です。

仏具の配置
仏壇に並べる仏具は、基本的に次のように配置します
花立(花瓶):左右一対で、仏壇の両端に置きます。片方だけの場合は向かって左に。
香炉:中央に置き、線香を立てるために使用します。
燭台(ローソク立て):香炉の左右に配置し、灯明として火を灯します。
供物台:果物や菓子、精進料理などを供える場所で、ご本尊や位牌の手前に置きます。
茶湯器・仏飯器:仏様にお茶やご飯を供える器で、中央やや手前に配置します。
お彼岸の供物
お彼岸には、特別なお供え物を準備することが習わしです。代表的なのは「ぼたもち(春)」「おはぎ(秋)」で、これは小豆の赤色が邪気を払うと考えられているためです。他にも、季節の果物や精進料理(肉魚を含まない料理)を供えると良いでしょう。



供物は奇数で
一般的に供物の数は縁起のよい奇数(1、3、5など)で揃えるのが良いとされています。
花の選び方と飾り方
仏壇に供える花は、「仏花」として特に清らかで落ち着いた印象のものが選ばれます。お彼岸には、季節感を大切にしながら、以下のような点に注意して選びましょう。
選んでよい花


リンドウ:秋の花で、清らかな印象。菊(特に小菊):長持ちし、仏事によく使われます


カーネーション:淡い色なら問題ありません。ユリ:香りが強すぎなければ、白ユリは適しています。
避けたほうがよい花
トゲのある花(バラなど):仏壇には不向きとされています。
毒のある花(スイセンなど):仏様に供えるには不適。
香りの強すぎる花:場の落ち着きを損なう可能性があります。
飾り方のポイント
花立に飾る際は、花が正面から美しく見えるように意識し、左右対称に活けるのが基本です。
花瓶の水は毎日替え、枯れた花はすぐに取り除きましょう。
仏壇のサイズに合わせて、花の高さやボリュームを調整します。
造花の仏花を使うメリット
- 長持ち:枯れずに美しさを保てる
- 経済的:頻繁に買い替える必要がない
- 手間が少ない:水替えや手入れが不要
■ 注意点
- 仏壇・お墓の雰囲気に合ったものを選ぶ
派手すぎず、落ち着いた色合いや仏事にふさわしい花を選びましょう。 - 定期的にホコリを払う
造花はホコリがたまりやすいので、清潔さを保つことが大切です。 - 宗派や地域の考え方に注意
一部では「生花で供えるのが本来の礼」とされることもあるため、気になる場合はお寺や年長者に確認を。

お彼岸の仏壇飾りで気をつけるべきポイント
食べ物は放置しない
長期間供えっぱなしにせず、悪くなる前にお下がりとしていただきます。ご先祖様と食事を分かち合う気持ちが大切です。
仏壇の掃除を事前に行う
お彼岸に仏壇を飾る前には、必ず仏壇の掃除を行いましょう。ホコリや汚れを丁寧に拭き取り、仏具も磨いて清浄な状態に整えます。
火の取り扱いに注意
ローソクや線香を使用する際は、火の元に十分注意しましょう。仏壇の周囲には燃えやすいものを置かないようにし、使用後は必ず消火を確認してください
宗派の作法に従う
仏壇の飾り方や仏具の種類は、宗派によって異なります。浄土真宗では線香を寝かせて供えるなどの違いがあるため、自分の家の宗派の作法を確認しておくことが大切です。
家族で供養の気持ちを共有する
仏壇を飾ることだけが目的ではなく、ご先祖様に対する感謝の心を家族で共有することが最も大切です。子どもや若い世代にもその意味を伝えながら、お彼岸を過ごしましょう。

まとめ

お彼岸の仏壇飾りは、ご先祖様に感謝の気持ちを表す大切な儀式のひとつです。花や仏具の配置、供物の選び方、掃除や火の管理など、細やかな心配りが求められます。形式だけにとらわれず、気持ちを込めて仏壇を整えることが、何よりの供養となるでしょう。お彼岸を機に、今一度自分と先祖とのつながりを見つめ直す時間を持ってみてはいかがでしょうか。


