お盆と言えば盆提灯を飾ってご先祖様をお迎えする日本の伝統的な文化です。お盆の期間中、故人やご先祖様の霊がこの世に帰ってくると考えられており、盆提灯の明かりは霊が迷わず家に戻れるようにする目印とされています。 盆提灯には、お盆が始まる際の故人の道しるべとなる 「迎え火」と、お盆が終わる際の魂を送り出す 「送り火」 としての大切な役割があります。そしてその形や使い方には地域ごとの違いがあり地域性が色濃く表れています。そんな盆提灯の地域性について紹介していきます。
地域別の特徴
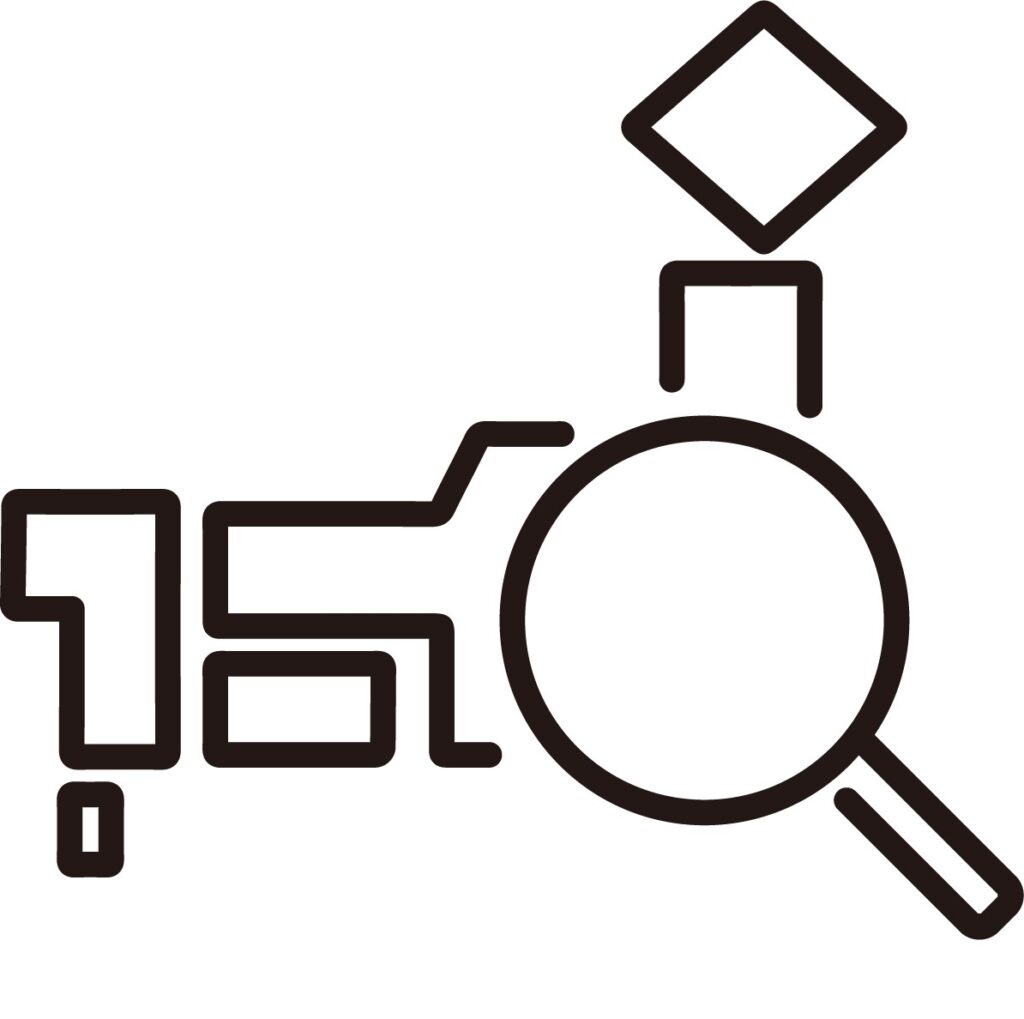
東日本(関東・東北など)
新盆(初盆)に特に重きを置き、白い提灯(白提灯)を一対用意するのが一般的です。他にもさまざまな特徴があります。

- 新盆の白提灯は一度だけ使用し、お盆が終わったらお寺などでお焚き上げをする。
- 提灯は吊るすタイプが多い(玄関先、軒先など)。
- 東京など都市部ではコンパクトな提灯やLEDタイプも増加中。
名産地:茨城県水戸市、岐阜県岐阜市
茨城県水戸市と岐阜県岐阜市はそれぞれ日本三大提灯の一つです。水戸市は水府(すいふ)提灯の名産地です。水府とは江戸時代の水戸の別称です。水戸藩の下級武士が生活を支えるため励んだ提灯作りがその発祥とされます。「一本掛け」という独自の手法で作られており、勢いよく引き伸ばしても形が壊れたり紙が破れたりしない耐久性と耐水性が特徴です。また岐阜市は岐阜提灯の名産地で、美濃地方の薄く高品質な美濃和紙や竹などの資材が豊富にあったことから発展しました。風景などの絵付けが施され繊細で美しい火袋が特徴です。
西日本(関西・中国・四・九州など)
関東で初盆を大切にするのに対して、白提灯よりも華やかな絵柄入りの盆提灯が好まれる傾向があります。

- 吊るすタイプだけでなく、床置きタイプ(回転灯など)も多く見られる。
- 家紋入りの提灯を用意する家も多い(特に関西や九州)。
- 提灯は毎年同じものを使い、お盆のたびに飾る。
名産地:福岡県八女市
福岡県八女市は日本三大提灯である八女(やめ)提灯の名産地です。八女提灯は一本の細い竹ヒゴを螺旋状に巻きつけることにより製作する「一条螺旋式(いちじょうらせんしき)」の竹骨と花鳥や草木の美しい彩色画が施された火袋が特徴です。
地域によって異なるお盆の時期
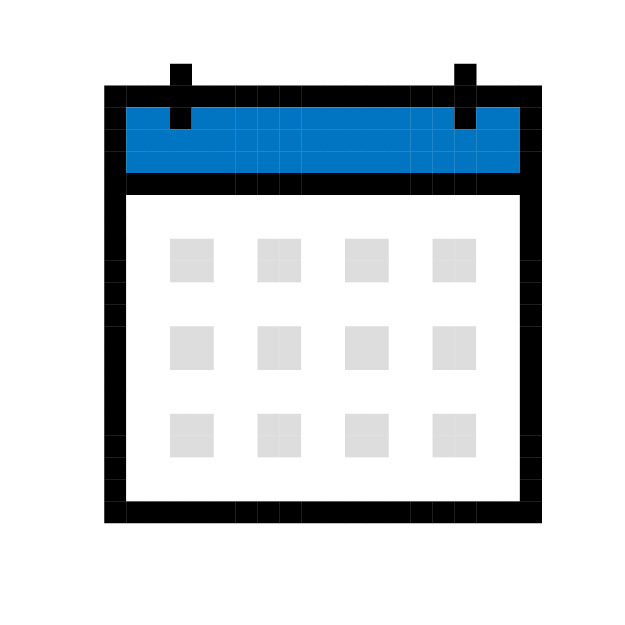
お盆の時期が地域によって違うのには、歴史的な背景とカレンダー(暦)の違いが関係しています。昔の日本では「旧暦(太陰太陽暦)」が使われていて、旧暦の7月15日は現在の暦(新暦)でいうと8月中旬ごろになります。明治時代に日本が新暦(太陽暦/現在のカレンダー)に切り替えたとき、旧暦の7月15日をどう扱うかで地域ごとに対応が分かれました。明治政府の影響で早くから「新暦」を取り入れていた都心部ではそのまま7月盆に移行した一方、地方では7月15日ごろは農家の繁忙期にあたることから8月盆を選ぶ地域が多かったようです。
| 時期 | 期間 | 地域 |
|---|---|---|
| 7月13日〜7月16日 新盆、7月盆 | 7月15日を中日とした前後4日間 | 東京都、神奈川県・横浜市、北海道・函館市、石川県・金沢市、静岡県の一部地域など |
| 8月13日〜8月16日 8月盆 | 8月15日を中日に前後4日間 | 全国的に多く、新盆や旧盆以外のすべての地域 |
| 8月の3日間(不規則) 旧盆 | 7月13日〜7月15日の3日間を新暦に当てはめて行う | 沖縄県、鹿児島県・奄美群島など |
盆提灯の種類とデザイン
大内行灯(おおうちあんどん)

足が3本ある置き型の盆提灯の1つで、一般的には高さが80cm〜120cm程度と比較的大きめです。提灯の上部には雲手が付いています。 「大内」は、室町時代に権勢を誇った大内氏(特に山口県あたり)に由来するとされます。当時、大内氏の屋敷に置かれていた格式高い行灯にちなんで名付けられたという説が有力です。 火袋の絵柄が正面にくるように飾り、仏壇の左右に対に置くのが一般的ですが、決まりはありません。
回転行灯(かいてんあんどん)

行灯の中にロウソクや電球などの光源があり、その熱で内部の「風車」のような羽根が回転します。羽根には軽い素材が使われ、熱によって中の部分がくるくると回転する仕組みの行灯です。納涼感があり、暑いお盆の時期に飾ると涼しい気分になります。
住吉行灯(すみよしあんどん)

新盆行事の盛んな九州、博多の住吉町で使われはじめた提灯で、仏壇の両サイドに飾る縦長の円筒形の長細い形状が特徴です。主に九州や山陰・山陽地方、茨城など北関東地方の一部で用いられる事が多い提灯です。
まとめ

盆提灯のデザインや飾る時期は地域毎に異なり、地元の風習や伝統、都市部と地方の持つ生活スタイルの違いなど様々な要因が絡んでいることがわかりました。それぞれの名産地には素晴らしい特色や技術があります。その地域に根差した伝統を盆提灯を通して学んでみてはいかがでしょうか。


