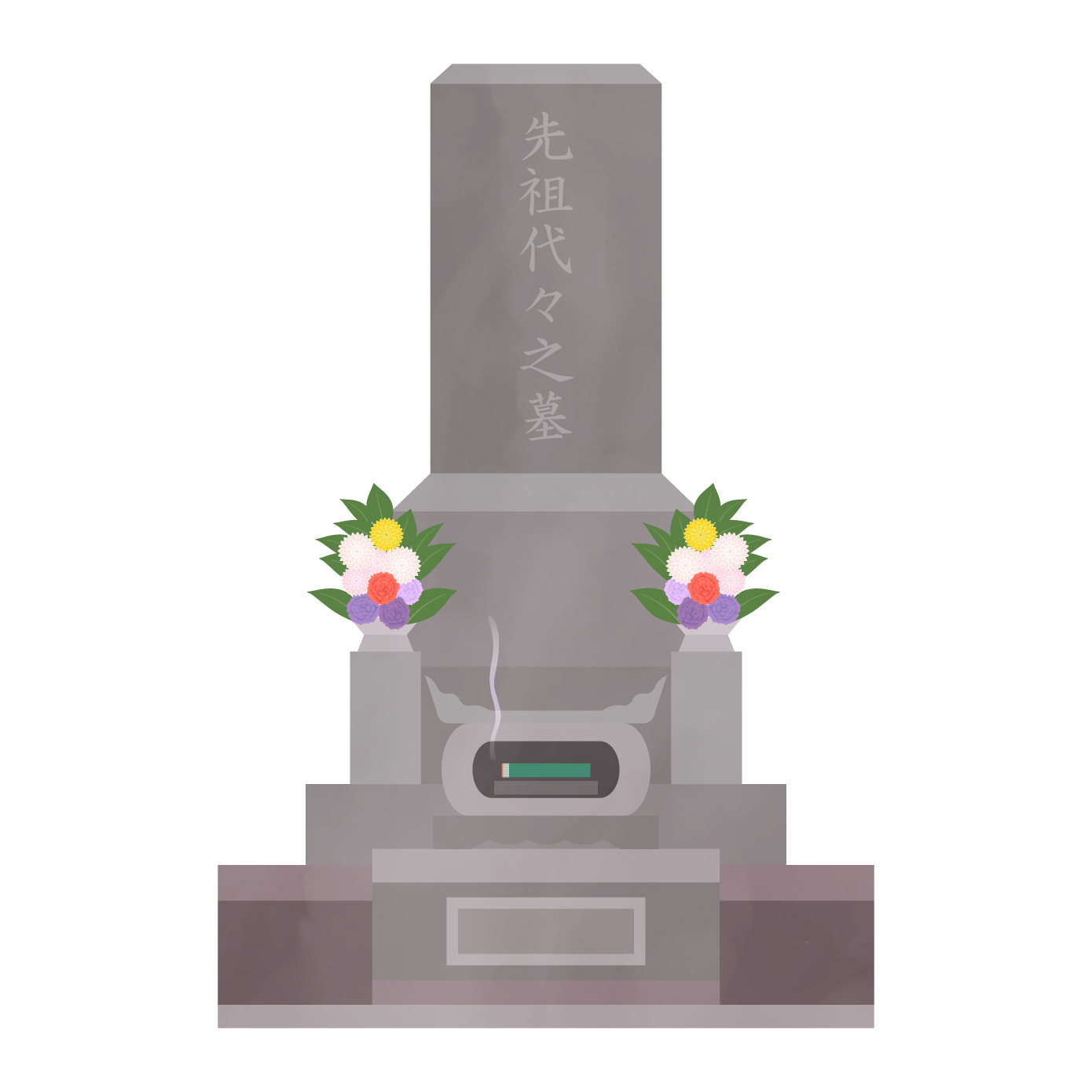「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますが、お彼岸のそもそもの意味を説明することができる方は少ないのではないでしょうか。お彼岸=お墓参りと認識している方も多いでしょう。お彼岸は単に特定の期間や行事を指すだけでなく、仏教の深い教えとともに、先祖や自然とのつながりを再確認する大切な言葉です。そんなお彼岸について詳しく解説していきます。
お彼岸とは

宗教的・思想的背景
彼岸の意味
「彼岸」という言葉は、インドの古典語であるサンスクリット語で「悟りの世界」を意味する言葉で本来、悟りや涅槃といった理想的な境地を表す仏教用語です。pāramitāw(パーラミター)※漢語:波羅蜜の漢訳語「到彼岸(とうひがん)」からきています。彼岸は、迷いや煩悩のない悟りの境地です。一方私たちの世界は「此岸(しがん)」と呼ばれ、煩悩や欲の存在する世界になります。此岸と対比して、迷いや苦しみから解放された「彼岸」に到達することが理想とされます。その修行をする期間がお彼岸なのです。

お彼岸の行事としての意味
実はお彼岸の習慣は、ほかの仏教国にはなく日本独自の仏教文化の一つなのです。お彼岸の期間は、先祖供養や仏教の教えを振り返る良い機会とされ、家族や地域で墓参りや供養、法要などが行われます。また彼岸の仏事を彼岸会(ひがんえ)と呼び、お寺の敷地内で合同法要(合同供養)が行われることがあります。先祖への感謝の気持ちを表すとともに、今の自分たちの生き方や精神性を見つめ直す時間とされています。
お彼岸の期間
お彼岸の期間は、1年に2回「春」と「秋」にあります。この期間は、太陽が真東から登り、真西に沈む日であることから、昼と夜の長さがほぼ等しくなり彼岸と此岸が最も近づく日と考えられています。
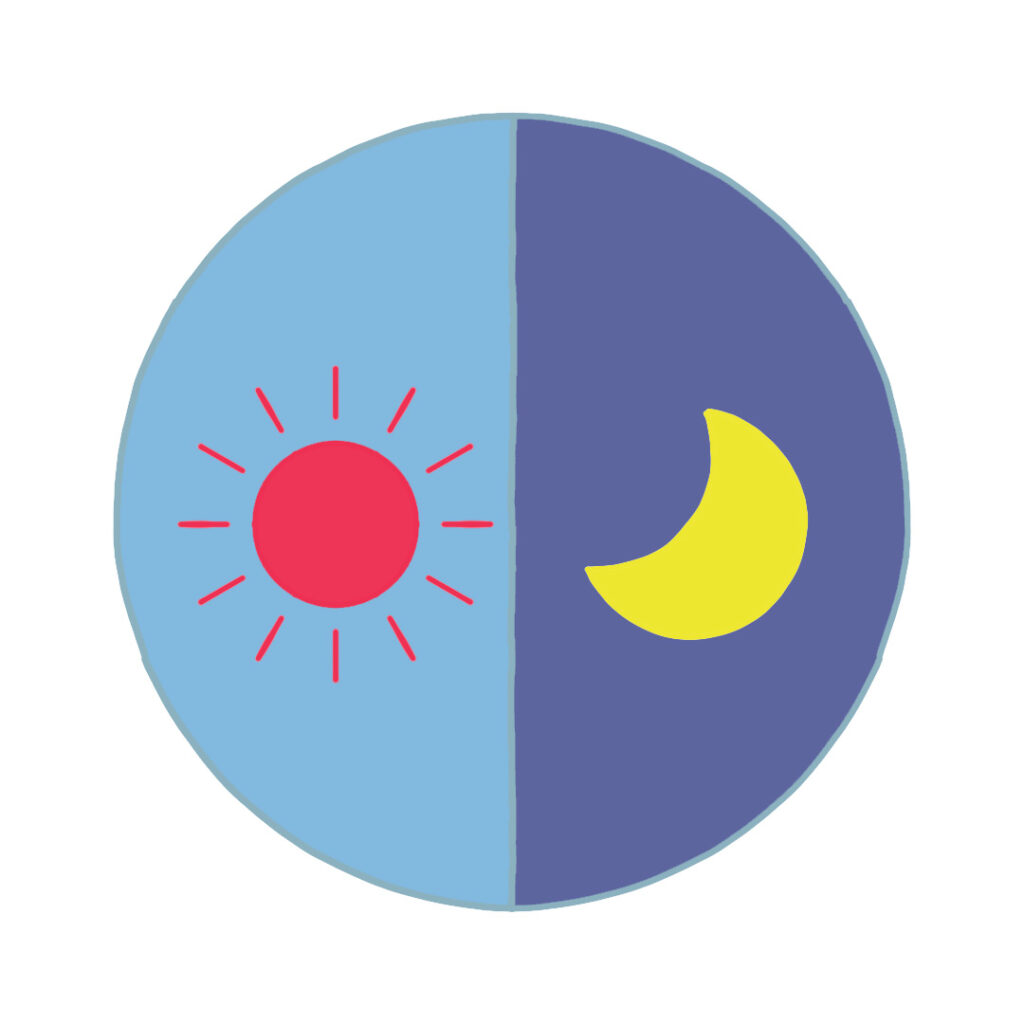
春のお彼岸
3月の「春分の日」を中心とした前後3日間、合計7日間。新しい季節の始まりとともに、生きとし生けるものの命の循環や再生を感じる時期です。
秋のお彼岸
9月の「秋分の日」を中心とした前後3日間、合計7日間。夏の暑さが去り、自然が静かに実りを迎えるこの時期は、過ぎ去ったものや先祖への想いを新たにする時とされています。
お彼岸には何をするの?
墓参り

お彼岸は仏の入滅時にお顔が西に向いていたことから西にあるとされる極楽浄土に思いをはせるのにふさわしい時期とされています。また前述した通り、春分・秋分の日周辺は彼岸と此岸が最も近づく日と考えられています。彼岸が近くにあることによりご先祖に思いが届きやすいという考えもあります。そのため期間中、多くの家庭が墓地を訪れ、墓の掃除や花供え、お線香をあげるなどして先祖を敬います。
▼プラスチック製手桶(ひしゃく付き)※名入れも承っております

六波羅蜜行

仏教ではお彼岸の期間=修行の期間としても位置付けられています。悟りを開いて仏になるために弟子や仏教徒はお彼岸の期間中、修行に励みます。そこでお釈迦さまは、私たちが実行しやすいように、善を6つにまとめられました。それが六波羅密です。簡単に言うと【悟りを開くための6つの実践項目】です。
- 布施……親切。見返りを求めず、惜しみなく他者に施しをすること。
- 持戒……言行一致。自分の行動を律し、正しい道を歩むことで清らかな心を育む。
- 忍辱……忍耐。侮辱や困難に対して怒らず、穏やかに受け入れる。
- 精進……努力。常に向上心を持ち、怠らずに実践し続ける。
- 禅定……反省。瞑想を行い、心を安定させること。
- 智慧……修養。物事の本質を見抜く智慧を持つこと。
お彼岸の期間中、中日はご先祖様に感謝し、残りの6日間はこれらの修業を一日一つずつ行うことで、仏の悟りの境地すなわち彼岸に近づくことができるとされています。「修業」と聞くと、僧侶でもない私たちには関係のないことのように思えるかもしれません。しかしこれらの教えは現代を生きる私たちも身に着けるべき人としての善い行いなのです。あまりにもたくさんの項目があると億劫になってしまいますが、善が6つにまとめられているのですぐにでも取り掛かることができます。人に親切にする、宣言したことを最後までやり通すなど実践できることはたくさんありますよ。
まとめ

お彼岸はお墓参りをする、などの単なる慣行の行事や期間を表す言葉ではなく、宗教的背景に基づく意味があることがわかりました。また仏の教えを深める機会とされています。日本独自の仏教行事ですが、その根底には仏教の「悟りへの道」や「先祖への感謝」という精神が息づいています。この期間に自分自身の生き方を見つめ直し、より善い行いを心がけでみてはいかがでしょうか。